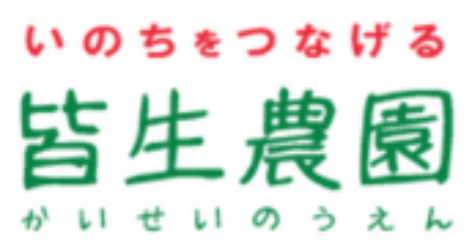昨年から急に米の値段が上がり始めた。生産量の減少にくわえ、中間卸業者や米を使う外食産業、さらには消費者の買いだめが原因らしい。米不足の危機感は石油ショックの時のトイレットペーパーの比ではない。
今から40年前の1985年、ソマリアの難民キャンプで活動中に今起きている事態を予見し、私は就農しようと決めた。
実際、1980年代から、日本の農業は衰退の一途をたどってきた。1984年に日本の農業生産額が11.7兆円でピークをつけ、それ以降は減少してきた。2010年には8.1兆円に落ち込んだ。2020年のコロナ禍前後から若干は増加したものの、他産業から比べれば微々たるものである。
なぜこうなってしまったのか。
私は、2020年から21年にかけ、その衰退の原因を整理してみた。(第342話から第358話まで)
それらは、①きわめて低い農業所得、②過酷な労働環境、③アメリカの食料戦略、④産業構造の変化と農業の機械化、⑤不適切な政策、⑥消費者の関心の薄さ、⑦耕作条件の悪い農地、⑧気象条件、⑨食事内容の変化、⑩食に対する意識の変化である。他にもいくつか思い当たるものの、主な原因はこれらだろう。
唯一自給してきた米の供給不足が顕在化した今、これら衰退の原因が今後どのように推移し、日本農業にどう影響するか考察してみたい。
その際、3つの前提を設定しておく。①世界の穀物生産量に大きく影響するような異常気象が発生しない。②ウクライナ戦争やコロナ禍のように穀物の輸出や海上輸送に大きく影響するような事態が起きない。③日本政府の農業政策が大きく変更されることがない。
次回から具体的に見ていきます。
(文責:鴇田 三芳)