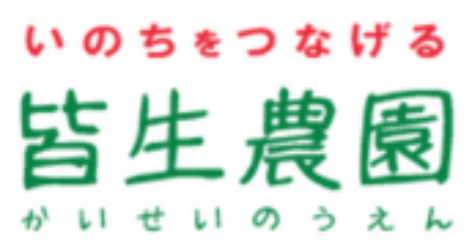農業の衰退を止めるには、少なくても、3つの改善策が必要と私は思っている。
まず今話では、新規就農者への公的支援の拡充について述べたい。
私は、脱サラし、1990年に就農した。当時はバブル経済のピーク時で、農家や不動産業界、金融機関などは農地を宅地化することに血眼になり、新規就農者など見向きもされなかった。何しろ、宅地化すれば農地の価格が3桁も4桁も値上がりしたのだから、農地を農地として貸したりはしなかった。
そんな社会的な背景があり、新規就農者への公的支援は非常に限られていた。私が受けた公的支援は、居住地にあった千葉県東葛地区農業改良普及が船橋市内の研修先を紹介してくれたことと、市立船橋農業センターが無料で土壌調査をしてくれたことの2つだけだった。どちらもありがたかったが、資金支援もあれば受けたかった。
こんなこともあった。就農3年目に農家資格をとろうと船橋市役所の担当課を訪ねたが、どんな手続きをしたらいいのか担当者ですら知らなかった。愕然とした。後で近所の農家に憤懣(ふんまん)をぶちまけたら、「新規就農者に農家資格を与えたって税収は見込めないけど、農地を宅地化すれば、多額の税金ががっぽり転がり込んでくるからな」と言われてしまった。
時は流れ、今では「青年就農給付金」などの資金支援制度がある。研修期間中に最大2年間、独立後に最大5年間、合計7年間にわたり毎年150万円の給付を受けられる。
さらに、各都道府県には公立農業大学校があり、基礎知識を習得できる。実際、私のところへ研修しに来た人の内、3名はそこの卒業生だった。
それでもなお、これらの支援制度を改善する必要があると私は思っている。青年就農給付金については、給付期間の1.5倍(最低2年間)の期間以上就農を継続しないと支給金の全額を返済しなければならない。つまり、4年間給付を受けたら、給付終了後6年間は営農し続けなければならない。
しかし、支給にあたっては審査を受けるのだから、返済義務など撤廃すべきである。それでなくても、農業はあまり儲からなく、新規就農者は大きなリスクを覚悟して人生の重要な選択をするのだから、返済義務を撤廃したところで何か問題があるのだろうか。
新しく入隊した自衛隊員がまともな戦闘員に育つまで何年もかかるだろう。多額の税金をつかってやっと一人前になった隊員が自衛隊を一身上の都合でやめた時、国はそれまで支払った給料を返却しろと言うだろうか。会社員も同様である。
近年、国民・国家の安全保障上5つの分野がきわめて重要と指摘されている。軍事、エネルギー、経済、食料、そしてサーバー空間。そんな重要な農業にチャレンジする新規就農者への支援は未来への国家的投資なのである。
また、一定の要件を満たせば、公立農業大学校の授業料は無料にしてもいいのではないか。私がそう考える根拠は労働省が管轄する「求職者支援制度」にある。この制度では、一定の要件を満たせば、再就職、転職、スキルアップを目指す人に月10万円生活支援金が支給され、無料の職業訓練を受けられる。
さらに、まともに営農している農家や農業法人を研修先としてもっと積極的に紹介してもらいたい。新規就農者にとって研修は、実践的な技術を習得するうえで非常に重要であり、研修後の営農に大きく影響を及ぼすのだから。
(文責:鴇田 三芳)