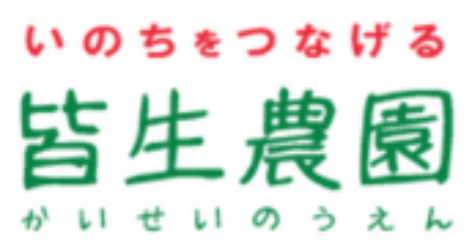農業の衰退を止めるには、少なくても、3つの対策が必要と私は思っている。
今話では2つ目の対策「所得補償」について述べたい。
2009年9月から3年3か月、民主党が政権を握った。その間の政策の一つが農業者戸別所得補償だった。政権をとる前の民主党は専業農家のみを補償対象と主張していた。しかし、いざ政権を握った後に民主党は、農家に占める専業農家の割合があまりにも少ないために、また足元の自分たちの票を得るために、兼業農家や零細農家も含めて特定作物を生産する全農業者を対象にした。その結果、それまで自分では耕作していなかった名ばかり農家が、補助金目当てに貸していた農地の返却を求めたり、形ばかりの耕作をし始めた。選択・集中の政策からバラマキ政策へと変質してしまったことにより、それまで進めてきた農地の大規模化政策に逆行することになった。私は明らかに失政と思っている。
民主党政権があっけなく倒れ、復活した自民党と公明党の連立政権が所得補償制度を見直し縮小したものの、一定の条件を満たせばどんな農家にも支給するバラマキ状態は続いてきた。
こんなことで、日本の食料自給率が上がるはずもない。
私が思う所得補償制度は、山下一仁氏(元農林水産省のキャリア官僚で現在はキャノングローバル戦略研究所研究主幹)がかれこれ20年近く主張してきたこととほぼ同じで、実際に販売用の農産物を栽培している農家に所得補償を直接支払うことである。この制度は、すでにEU諸国やアメリカで広く実施されてきた。フランスでは農家収入の8割、アメリカの穀物農家の収入の5割前後が政府からの補助金と言われている。
この案で明確にしなければならないのは、「どのような農家にどの程度の所得補償をするか」という点である。
「どのような農家」という点では、農業所得(収入から経費を差し引いた額)のある農家を対象とすべきだろう。頑張って農業所得を増やせば、それに応じて補助金も増えるので、営農意欲が増し、必要性の乏しい支出が減る。もちろん、形だけの農家で実際には耕作していない農家や赤字の農家は排除すべきである。
「どの程度の所得補償をするか」という点では、所得の3割くらいから始めるのが現実的ではないだろうか。所得が200万円の農家には60万円の支給となる。
この制度の対象者には漁業者や林業者も同等に含まれるべきと思う。
この制度には税金という国民負担が増えるものの、農林水産業の生産者の所得余裕が生まれることで農林水産物の物価が下がり、税金は国民に還元される。とりわけ、エンゲル係数の高い低所得者への恩恵が大きいメリットがある。
この制度によって、農家の所得が増え、自給率が上がり、農林水産物の価格が下がる(あるいは値上がりが止まる)。まさに、一石三鳥である。
(文責:鴇田 三芳)