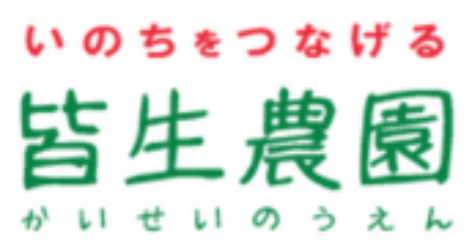農林水産省のデータ((5)農業所得:農林水産省)を見ると農家の所得がだいたいわかる。
農業の実態を知らない人は驚かれるだろうが、農産物の売上額が300万円以下という経営体(農家)が圧倒的に多い。もちろん、この売上額には経費も含まれるので、手元に残る手取り額(所得)は半分くらいになる。このような状態の農家は農業だけで食えるはずもない。さらに統計の中では、農産物の売上額が50万円以下の農家がもっとも多い。とても農家とは言えない規模である。
このような現実を反映してか、農産物の売上額300万円以下という農家が激減していることもデータからわかる。農家の平均年齢が70歳前後という実態を考慮すれば、たぶん、売上額が少なくて辞めていく農家・農民のほとんどは高齢化した人たちだろう。体力の衰えを実感している72歳の私には大いに納得できるデータである。
さらに、農林水産省のデータから、営農規模が大きくなるとともに所得が増える傾向にある。私と同じ露地野菜の栽培では、15~20haの経営体では、所得が1000万円をわずかに超えている。この額は大きいように見えてしますが、実は農林水産省のこのデータにはもっとも重要はデータがのっていない。それは、「一人がいくら稼いでいるか」というものである。
私の経験と知見から、20haもの露地野菜を生産し販売するには、どんなに機械化していても、一人では絶対に無理である。非常に手慣れた優秀な農民たちでも、5人くらいは必要であろう。かりに5人とすれば、一人当たりの年間所得は200万円ほどになる。これでも、農家としては所得が多いほうである。(私ごとになるが、パート従業員を4~5名雇用している私の年間所得は200~250万円である。)
週休2日もなく、労働保険(雇用保険と労災保険)も身分保障もなく、過酷な労働条件で働く者の年間所得が200万円。皆さんはどう思われるだろうか。
こんな状況で意欲に燃えた優秀な若者が就農するだろうか。
では、所得の少ない状況をどのように改善すればいいのだろうか。次話に3つの改善策を述べてみたい。
(文責:鴇田 三芳)