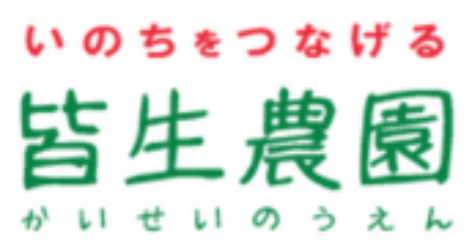40年ほど前、私はアフリカのソマリアにあった難民キャンプで難民への支援活動に携った。その時、「日本もいずれ満足に食料を買えない時代が来る」と直感した。GDPがアメリカに迫り日本中がバブル経済に浮かれていたが、いずれバブルがはじけ経済力が衰退すると思ったからだ。(実際、その後10年もたたずに、そうなった。)
帰国後の1987年、専業農家であった家族にその直感を話したが、まったく相手にされなかった。「かつての太平洋戦争のような事態でも起きない限り、日本人が食べ物に困るようなことは絶対にない。米なんか余ってしょうがないんだ」と一蹴された。
しかし、その6年後の1993年、それまで米あまりで困っていた日本が米を緊急輸入せざるをえなくなった。80年ぶりの大冷夏によって、その年の収穫量は平年の70%ほどしかなかったからだ。大冷夏の原因は、1991年6月に起きたフィリピンのピナツボ山の大噴火で大気中に細かな火山灰が滞留し太陽光をさえぎったためと言われている。その年の9月、細川内閣はタイ、中国、アメリカなどから合計259万トンの米を緊急輸入すると発表した。
幸いにもそれ以降、日本人が米不足で困ったことはなかった。食料自給率が40%を切っている日本でも、米だけは唯一自給できている。そのこともあってか、米価はバブル経済が崩壊し始めた1993年をピークに下がり続けてきた。
しかし、昨年夏から米の価格が上がり始め、現時点では前年比の2倍ほどにも高騰している。生鮮野菜が2倍に高騰するのはよくあるが、米が一気に2倍になることなどなかった。いったい誰がこんな事態を想像しただろうか。
高騰の原因はいくつか世間で言われているが、根本的原因は、消費者に搾取され続けてきた農家がどんどん止めていくことにある。米の末端価格が2倍になったところで、米農家の減少は止められない。末端価格が2倍になっても、米農家の販売価格は大して上がらず、収入が増えた分の多くは肥料や資材、燃料代などの経費の増加分が相殺してしまうからだ。
ロシアによるウクライナ侵略によって世界情勢は緊迫の度を増し、くわえてトランプ大統領による輸入関税の急激な引き上げが世界経済を悪化させつつある。とりわけ、先進国の中でも日本と韓国は悲惨な時代に突入した。カナダや中国などの国々はアメリカに対抗措置をとったが、日本には何も打つ手がない。できるはずもない。貿易も軍事も食料も、そしてエネルギーもアメリカに大きく依存しているからだ。
このままトランプ大統領が関税政策を緩めなければ、日本経済は大きなダメージを受け、さらなる円安になり、輸入物価の高騰が続くだろう。さらなる物価高騰に対して、日本政府や日銀はなす術もない。物価高騰を抑えようと政策金利を無理して上げたところで、物価の高騰は抑えられない。
結局、給与所得者の実質賃金が下がり続け、庶民の家計はさらに悪化するのは間違いない。
その一方で、農産物の国内生産量は減り続け価格は上がっていく。農家の減少が止まらないからだ。
家計の悪化と食料品の価格高騰によって、日本の庶民は満足に食料品が買えなくなりつつある。日本人の飢餓がすぐそこまで来ている。
(文責:鴇田 三芳)