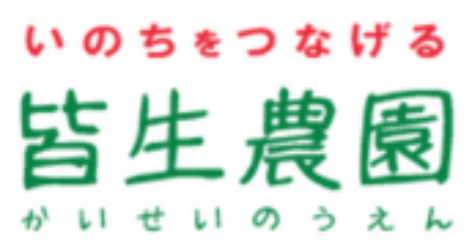新しい生活でストレスをため「5月病」にかかった新社会人も少なからずいるだろう。厚生労働省のデータによると、新卒者が3年以内に離職する割合は少しずつ増え続けいるという。直近では大卒者が3割強、高卒者が4割強も3年以内に離職し、従業員数が少なくなればなるほど離職率が高い。ほとんどの若者にとって、学校生活から仕事生活に移ることは容易ではないからだ。
学校では、過去の結果を教えられ記憶し、その範囲内の問いに答えれば良い。ほとんどの問いに答えは一つしかない。単純なプロセスで評価される。
しかし、仕事は違う。勉強のようなプロセスーーー単純な一方向のプロセスだけでは済まされない。ときには自分で問題を発見し課題を設定し、すでに獲得している知識や経験はもちろんのこと、新たに必要な情報を集め想像力を働かせなければならない。教えられたことだけをただただ繰り返すような仕事は機械に置き換えられてしまう。
さて今話の本題に。
仕事を大別すると、以下のような4種類のようにも分けられると私は思っている。
①自分や家族の利益にも、社会にも役に立つ仕事。
②自分や家族の利益にはなるが、ほとんど社会の役に立たない仕事。
③たいして自分や家族の利益にならないものの、社会の役に立つ仕事。
④たいして自分や家族の利益にならないばかりか、ろくに社会の役にも立たない仕事。
私がかかわっている農業を上記の分類から概観してみよう。
まず①としては生活を維持できる所得を得ている農家だろう。②は農林水産省が「自給的農家」と分類している農家だ。ほとんど販売せずに自家消費を目的として生産している農家がこれにあたる。③としては、農地を無料か廉価で貸している農家がこれにあたる。体力も機械もなくて耕作できないものの、耕作放棄地にはしたくないと考えている。最後の④に入るのは、耕作放棄地にしたくないと刈払機やトラクターで定期的に草対策をしている農家だ。
私の周辺では、かつては④の農家もそこそこいたが、今ではほとんど見かけなくなった。下の写真のように何もしないで大事な農地を放棄地にしているだけだ。このような状態にいたっては、もはや農家などとは言えず、社会悪となっている。

今話では農業について考えてみたが、次話からは他の産業についても考えてみたい。そして、私が考える仕事の本質を述べたい。
(文責:鴇田 三芳)