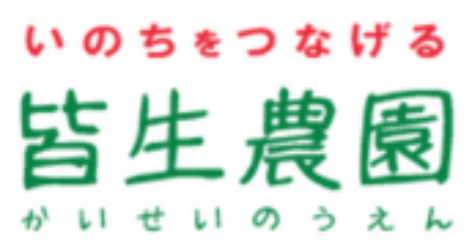食料品の値上がりが止まらない。特に米の値上がりは突出し、日本農業の衰退が国民全体に認識された。
その一方で、耕作放棄地は増え続けている。私の農地に隣接する耕作放棄地から葛(くず)がこちらに侵入してきて、今日、今年3回目の葛刈りをした。葛は丈夫な蔓(つる)なので、とても疲れる。

さて、今話では農業の衰退を止める3つ目の対策「農地の流動化」について述べたい。
日本では、非農家出身の者が農家(あるいは農業法人)として農業を営むのがきわめて難しい。その大きな原因は二つある。1つは施設や機械などの購入のために多額の初期投資が必要なこと。農家の子どもは、親が営んできた農業をそのまま継ぐなら、初期投資がほとんど要らないか少なくて済む。不公平のように思えるかもしれないが、この点は一般の会社でも同じだ。自分で会社を興そうと思えば、それなりの資金を用意しなければならない。
もう一つが大問題だ。それは農地の入手が容易ではないこと。私が就農したバブル経済絶頂期から比べれば、放棄地が増え続ける近年は入手しやすくなったとはいえ、非農家出身の者が優良農地を入手するのは今でも非常に難しい。
政府が長年唱えてきた「食料自給率の向上」は、農地の入手に苦労してきた私から見れば、絵にかいた餅に等しい。本気で日本の食料自給率を上げるのなら、行政法よりも根本的な憲法にまで踏み込む必要があると私は以前から思ってきた。例えば、憲法29条が保証する財産権を農地に限っては制限を加えるべきである。
憲法29条は3つの条文からなっている。その第3項に「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」とある。「農地は、完全な私有物ではなく、公共性がある」と私はかねがね思ってきた。ここ1年あまりの間に米価が2倍に跳ね上がり、ほとんどの国民が経済的圧迫を強いられている現実は農地の公共性を如実に物語っている。
そこで、現実的な施策を提案したい。農地を有効活用する農業者(農家あるいは法人)に対してだけその財産権を与え、有効活用していない農業者の農地は行政機関が安い価格で買い上げ、新規就農者も含めた農業者に安く貸し出す施策。その際の法律は「強制収用法」を適用したらどうだろうか。
あるいは、税制で実効させる方法もある。具体的には、すべての農地に一定額の固定資産税を課せばいい。その額は、耕作していない農業者(あるいは利益が出ていない農業者)が、税負担に耐えられず所有権を放棄したくなるくらいの額がいい。
これらの方法か、あるいは他の方法によって、農業をしたい人、農業を続けられる人に農地が容易に移転される「農地の流動化」が急務である。
(文責:鴇田 三芳)