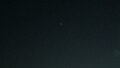1970年代後半から、日本の農業は衰退の一途をたどってきた。なぜこうなってしまったのか、農業現場から私なりに考えてきたことを述べてみたい。
前話では農業衰退の原因として食べ物の変化を指摘したが、今話では食べ物の変化の根底にある食べ物への意識・考え方の変化について考察してみたい。
日本人は何度も飢饉・飢餓を経験してきた。そのためもあって、明治維新後まず北海道へ開拓農民が入植し、その後アメリカや満州へも移住していった。日本では食っていけないからである。
そのころ、一部の権力者や富裕層を除けば、ほとんどの日本人は生きていくために食べていた。おいしいものや栄養豊富なものを食べる以前に、「まずは米を腹いっぱい食べたい」と、必死に新田を開発してきた。
ところが、前話で指摘したように、アメリカに敗れた反動もあってか欧米社会に強く憧れ、その先進性に魅せられ、彼らと同じような食べ物を追求してきた。「お米を食べるとバカになる。パンを食べなくてはいけない。」という世論が形成されたこともある。近年の世界的な和食ブームとは真逆である。
このような洋食化の流れの中で、日本人は食べ物への意識・考え方を劇的に変えてきた。「生きていくために食べる」という意識から、「健康により良いものを食べる」、「おいしいもの食べたい」、「時間を節約するために、手間暇かけず簡単に済ませる」、「自ら作るのではなく、出来上がったものを買う」という意識に変化してきた。これらの意識の変化によって、インスタント食品、冷凍食品、コンビニ弁当、お惣菜、サプリメントが売れに売れ、外食が大きく産業化した。はては、食べない(ダイエットや1食抜き)という食べ方まで社会に浸透した。
もはや、食べ物は、「作る」のではなく、「買う」ものへと変化した。食べることを、生きるための日々の営みと考えるよりも、利潤目的の企業活動と考えるようになった。となれば当然、企業は材料をより安く仕入れたくなる。バブル経済の崩壊によるデフレ経済も手伝って、農薬まみれだろうが何だろうが、とにかく安ければいいと食材の輸入が急増してきた。
その結果は明白である。こうして日本の農業は衰退してきた。
(文責:鴇田 三芳)